歓迎会に行きたくないと感じたときでも、うまく伝えれば評価を落とさずに断ることはできます。
なぜなら、歓迎会への参加はあくまで任意であり、丁寧に気持ちを伝えれば“協調性がない”と誤解されることは少ないからです。
私自身も、新人の頃に「今日はちょっと無理かも…」と思ったことが何度もありました。
お酒が苦手だったり、プライベートの予定があったりしても、「断ったらどう思われるか」が気になって、なかなか言い出せなかった経験があります。
この記事では、そんな不安を感じるあなたに向けて、歓迎会の断り方や理由の伝え方、印象を悪くしない工夫について具体的に紹介していきます。
気まずくならず、でも自分の時間は大切にする。
そのためのちょっとしたコツを、一緒に探していきましょう。
歓迎会や飲み会を断るのは勇気がいりますよね。
もしあなたが、こうした集まり以外にも職場の人間関係全般のストレスで悩んでいるなら、
全体像や具体的な対策をまとめた
職場での人間関係の悩みが尽きないあなたへ!心を守るヒントと具体的な対処法を紹介
も参考にしてください。
歓迎会に行きたくないときの断り方|角が立たない伝え方とは?
新しく職場に入ったばかりの頃って、何をするにも「これで大丈夫かな…」と不安になりますよね。
とくに、歓迎会のような「職場のイベント」は、自分の気持ちだけでは決めにくい場面です。
でも安心してください。
歓迎会に行きたくないと感じるのは、あなただけではありません。
そのうえで、角を立てずに気持ちを伝える方法は、きちんと存在します。
この章では、「歓迎会に参加したくない」と感じたときの考え方や、上手な伝え方について、順を追ってご紹介します。
歓迎会を断りたいのはおかしいこと?

「歓迎してもらってるのに、参加したくないなんて失礼かな…」
そう思って、モヤモヤしていませんか?
私も新入社員だったころ、「断ったら悪い印象になるかも」と何度も悩みました。
でも実際、同じように感じている人って、けっこう多いんです。
職場によっては、「飲みニケーション文化」が色濃く残っているところもありますよね。
ただ、時代とともに価値観も変化しています。
最近では、プライベートの時間を大切にしたい人が増えていて、「飲み会に行きたくない」という気持ちは、まったく珍しくありません。
SNSや掲示板を見てみると、「歓迎会って義務なの?」「行きたくないけど断れない」と悩む声がたくさん寄せられています。
そう、あなたが感じている葛藤は“ごく自然なこと”なんです。
むしろ、無理して参加して気疲れしてしまうより、心の声に正直になることのほうが大切な場面もあります。
大事なのは、「断るかどうか」ではなく、「どう伝えるか」。
ここから先は、相手に配慮しながら自分の気持ちを伝えるコツをお伝えしていきますね。
歓迎会を断るときに大事な3つの視点

歓迎会を断るとき、ただ一言「行きません」と伝えるだけでは、誤解を招くかもしれません。
上手に断るには、次の3つのポイントを意識することが大切です。
①🧑💼誰に伝えるか
👉 まずは 直属の上司やチームリーダーに伝えるのが基本!
周囲に自然と情報が広がることを見越して、
上司経由での共有がスマートな選択です。
②🕒いつ伝えるか
👉 タイミングは 早ければ早いほど良い!
直前のキャンセルはドタキャン扱いになりがち…。
予定が未確定でも「行けるか微妙で…」と事前に一言入れておくと安心です。
③🗣どう伝えるか
👉 キーワードは 「丁寧・簡潔・引き留めづらい理由」!
例:「家族の用事がありまして…」「体調を考えて控えさせていただきます」
さらに、「ご配慮ありがとうございます」など感謝の言葉も忘れずに。
たとえば…
- 「その日は家族の用事がありまして…」
- 「体調がすぐれない日が多く、今回は控えさせていただきます」
など、“相手が引き留めづらい理由”を用意しておくと安心です。
また、最後に「ご配慮ありがとうございます」や「お気遣い感謝します」と一言添えると、誠意がしっかり伝わりますよ。
相手に悪印象を与えない断り方の文例
断り方に自信がないときは、具体的な文例を参考にしてみましょう。
口頭や社内チャット、メールなど、状況によって伝え方も変わってきます。
ここでは、どの場面でも使える“丁寧で自然な断り方”の例文を紹介します。
【口頭で伝える場合】
「すみません、せっかくお誘いいただいたのですが、その日は家族の用事がありまして…。お気持ちはとてもありがたいのですが、今回はご遠慮させていただいてもよろしいでしょうか。」
【メール・社内チャットでの文例】
件名:【歓迎会のご案内について】
〇〇さん
お疲れさまです。△△部の□□です。
歓迎会のお誘い、ありがとうございます。
大変恐縮ですが、当日は私用の予定が重なっており、今回は欠席させていただきたく存じます。
お忙しいなかご調整いただいたにも関わらず申し訳ございません。
次の機会にはぜひ参加させていただきたく思います。
何卒よろしくお願い申し上げます。
いずれの場合も、「お誘いへの感謝」と「丁寧なお断り」がセットになっているのがポイントです。
断ることに後ろめたさを感じる必要はありません。
大切なのは、相手の気持ちにちゃんと向き合いながら、自分の都合を伝えること。
こうした伝え方を心がければ、関係を損なうことなく、不参加の意志を伝えることができますよ。
会社の飲み会を断る理由ってアリ?実例とリアルな本音
「体調不良とか家庭の都合って理由にしていいのかな…」
そんなふうに思って、断る理由を探す時間が長くなってしまうことってありませんか?
職場での飲み会を断ることに、罪悪感を感じてしまうのは自然なことです。
でも、実際には“ちゃんと理由を伝えれば”問題になるケースは多くありません。
このパートでは、よく使われている断り理由の実例や、評価に響かない言い訳のコツをご紹介します。
あなたが今感じている「モヤモヤ」の正体にも、きっと気づけるはずです。
「体調不良」「家族の用事」だけじゃない断り理由例
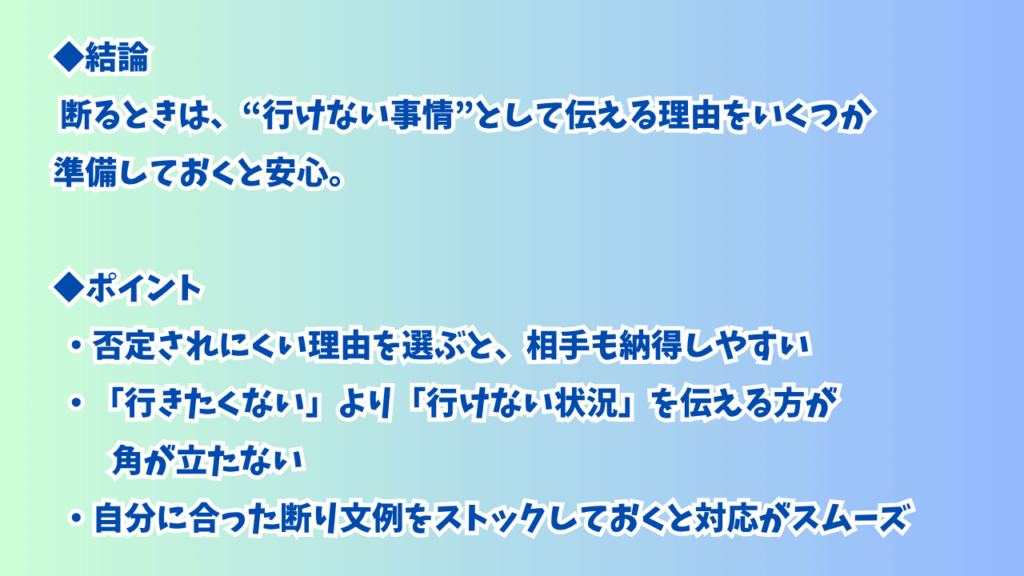
「断るとき、どんな理由を言えばいい?」
これは私も何度も考えたテーマです。
定番なのは「体調不良」や「家族の都合」ですが、それだけではバリエーションが限られてしまいますよね。
そこで、実際に使われているリアルな理由をいくつかご紹介します。
👪 家族の都合
・この日は実家に帰る予定がありまして…
・親の体調がすぐれず、付き添いが必要で…
🏥 体調・通院の予定
・通院の予約が入っていて、今回は控えたいと思います
・持病の関係で、夜の外出はできるだけ避けていて…
📚 勉強や自己研鑽(けんさん)
・資格試験の直前で、勉強に集中したくて…
・研修レポートの提出があり、この日は在宅で作業にあてたいと考えています
🐾 家事情・ペット関連
・飼っている犬の体調が悪くて、今日は付き添うことにしました
・子どもを迎えに行く予定がずらせず…
これらの理由は、“相手が否定しづらい内容”である点がポイントです。
また、明確に「行きたくない」と言うよりも、「行けない状況にある」というニュアンスにした方が、相手も受け入れやすくなります。
いくつか自分に合ったテンプレートを持っておくと、急な誘いにも落ち着いて対応できるようになりますよ。
断るときの“言い訳”はどこまでOK?

断る理由って、どこまで本音で言うべきなんだろう?
正直に「行きたくない」と言ったら、マズいのかな…?
そう感じたことはありませんか?
実は、職場での断り方においては、「少し曖昧な正直さ」が一番効果的なんです。
たとえば、「お酒が苦手で…」とだけ言ってしまうと、人によっては「少しだけでも来ればいいのに」と思われてしまうかもしれません。
でも、「翌日の体調に影響するので、夜は控えていて…」と伝えると、“事情がある”と納得してもらいやすくなります。
このように、“正直すぎず、ウソにも聞こえない”範囲で伝えるのがポイントです。
言い換えれば、
- ❌「行きたくないから行きません」
- ⭕「申し訳ないのですが、家庭の事情で夜の外出が難しくて…」
このくらいのバランス感覚があれば、相手との関係を壊すことなく断ることができます。
もちろん、あまりにも毎回同じ理由ばかり使っていると、信ぴょう性に欠けてしまうこともあるので、バリエーションは持っておくのがおすすめです。
断ったあとのフォローで信頼を保つには?

飲み会を断ること自体よりも、「その後どうするか」の方が大事かもしれません。
断ったことで相手に不快感を与えてしまった…そんな不安があるなら、ちょっとしたフォローで印象をガラッと変えることができます。
- 「お誘いありがとうございました。お気遣い、本当にうれしかったです」
- 「楽しそうですね!また機会があればぜひ参加させてくださいね」
こうした一言があるだけで、相手は「誘ってよかった」と感じてくれます。
また、翌日に
「昨日はありがとうございました!皆さん楽しそうでしたね」
「私も行けたら良かったです。またよろしくお願いします」
といった声かけをするのもおすすめです。
飲み会に行かなくても、日常のコミュニケーションで信頼は築けます。
むしろ、こうした“丁寧な対応”が、あなたの人柄を自然に伝えるきっかけになるかもしれません。
参加しないと「協調性がない」と思われる?

結論から言うと、飲み会に参加しなかっただけで「協調性がない」と思われるかどうかは、職場の文化と断り方によって変わります。
たとえば、私が以前勤めていた職場では、飲み会が“半分業務の延長”のような扱いになっていました。
断るときには必ず「また次回は行きたいです」と言っておかないと、「なんで来ないの?」と詰められるような雰囲気も…。
一方、今の職場では、参加はあくまで任意。
飲み会に来ない人に対しても「プライベートを大事にしてるんだな」と理解があります。
最近では、エン・ジャパンの調査(2024年)でも「職場の飲み会に参加しないことが評価に影響するとは思わない」と答えた人が全体の64%以上にのぼったそうです。
つまり、全体的には「飲み会不参加=評価ダウン」という時代ではなくなりつつあります。
とはいえ、まだまだ“付き合い重視”の空気がある職場もゼロではないのが現実。
だからこそ、丁寧な断り方が重要になってくるんです。
むしろ“断り上手”が信頼されることもある
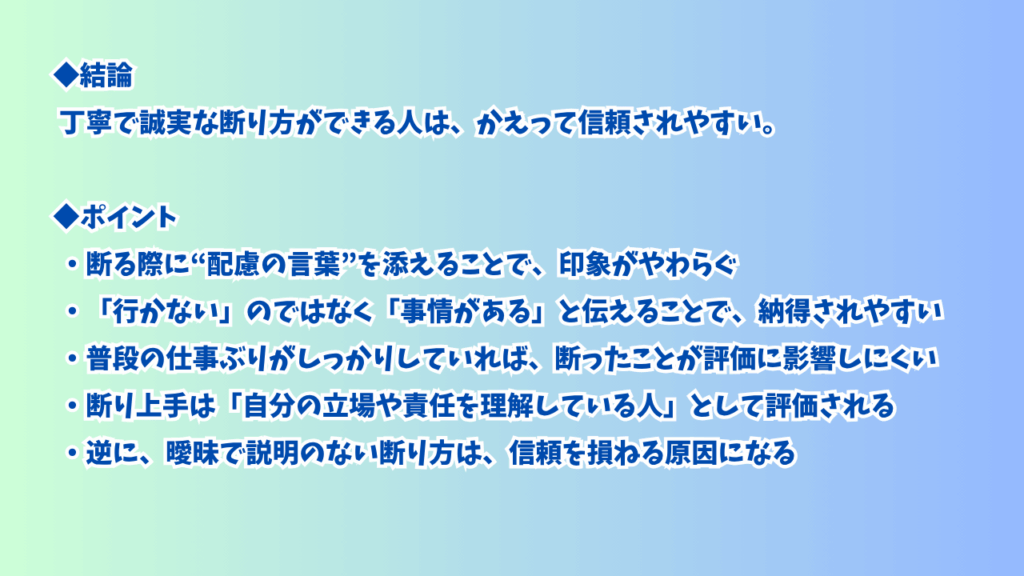
「断ること自体がマイナス」とは限りません。
むしろ、“断り上手な人”ほど、仕事で信頼されているケースもあります。
ある先輩は、家庭の事情で毎回きっぱり断っていました。
でも、その断り方がすごく自然で誠実だったんです。
たとえば…
- 「ありがとうございます。ただ、子どもがまだ小さくて夜は難しいんです」
- 「今は家族との時間を優先したいと思っていて…。でも、お誘いいただけたのは本当に嬉しいです」
そんなふうに、相手への配慮がしっかり伝わる言い方だったからこそ、周囲も「その人なりの事情」として受け入れていました。
逆に、「なんとなく行かない」人は、言い訳に聞こえてしまって評価を落としがちです。
つまり、丁寧に理由を伝え、普段の仕事でしっかり信頼を得ている人であれば、飲み会の不参加がマイナスになることはありません。
上手に断れる人は、「自分の立場や役割を理解している」と評価されることさえあるんです。
断り方ひとつで評価が変わる理由
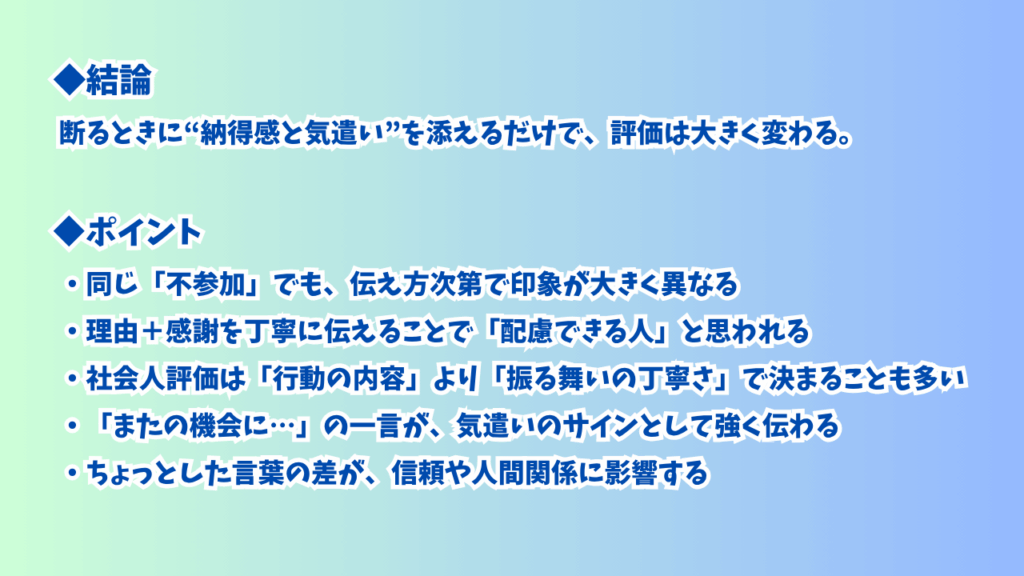
評価に差が出る最大の理由は、「納得感」と「気遣い」があるかどうかです。
断るときに、
- 無表情で「行けません」だけ伝える人
- 申し訳なさそうに理由と感謝を丁寧に伝える人
この2人では、相手に与える印象はまったく違います。
たとえば、後者のような伝え方ができると、「この人は相手の立場も考えられるんだな」と思ってもらえますよね。
社会人として評価されるのは、「何をしたか」だけではなく、「どう振る舞ったか」の方が大きかったりします。
私自身も、断るときには必ず一言添えるようにしています。
「今回はすみません。またの機会があれば嬉しいです」
その一言だけでも、相手の表情がやわらかくなるのを感じることがあります。
だからこそ、断るときは“そっと気持ちを添える”。
このひと手間が、あなたの印象を左右する大きなポイントになるんです。
歓迎会・飲み会の断り方がうまくなる5つのコツ
「断りたい気持ちはあるけど、どう伝えれば波風立たないんだろう…」
そんな迷いを感じている方のために、ここでは“上手に断るためのコツ”を5つに絞ってご紹介します。
どれもすぐに実践できるシンプルな方法ですが、ちょっとした言葉の工夫が、相手への印象を大きく変えてくれます。
一つでも取り入れてみると、あなたらしい自然な断り方がきっと見つかりますよ。
すぐ返事せず、少し間を置く
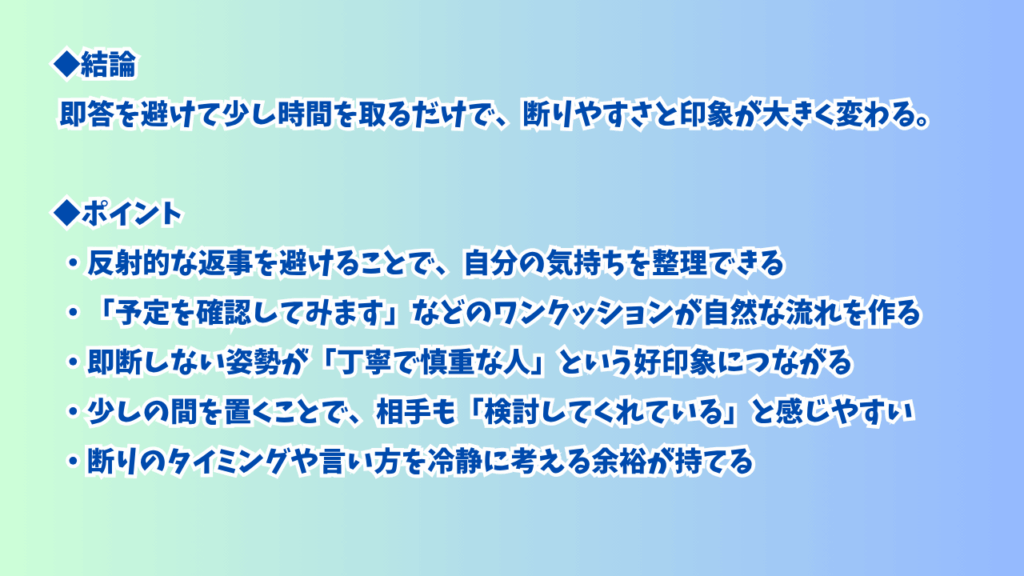
歓迎会や飲み会の誘いを受けたとき、つい反射的に「はい」や「ごめんなさい」と即答してしまいがちです。
でも、ちょっと待ってください。
すぐに答えを出さず、「少しだけ考える時間を持つ」ことがとても効果的なんです。
たとえば…
- 「予定を確認してみてもいいですか?」
- 「ちょっと調整できるか見てみますね」
こんなふうに、ワンクッション置くことで自分の気持ちを整理する余裕が生まれます。
即答すると相手も「じゃあ無理なんだね」と早々に判断してしまいますが、少し時間を置くことで自然に断りやすくなります。
また、“慎重な人”という印象も持たれやすく、雑な印象を与えません。
一度深呼吸して、「どう伝えるのが一番いいかな」と考えるクセをつけておくと、どんな場面でも落ち着いて対応できますよ。
「行きたい気持ちはあるけど…」の前置きが効果的
断りの言葉は、どうしてもネガティブな印象になりやすいもの。
でも、「行きたい気持ちはあるんだけど…」というクッション言葉を最初に置くだけで、グッと柔らかく聞こえます。
たとえば…
- 「せっかく誘ってもらって嬉しいんですが…」
- 「本当は参加したいんですけど、今回は…」
この一言があると、「誘って良かった」と相手に思ってもらえるんです。
私も以前、これを使うようにしただけで、断ったときの空気がまったく変わったのを実感しました。
表現は控えめでも、「あなたの気持ちはちゃんと受け取ってるよ」というサインを送ることが大切。
断り文句の前に“ひとさじの共感”を添えることで、伝え方がぐっと丁寧になります。
お礼と感謝を忘れない
断ることに集中しすぎて、「誘ってもらったことへの感謝」を伝え忘れていませんか?
飲み会の誘いも、相手からすれば“時間をかけて段取りしてくれた行為”のひとつ。
その労力に対してきちんとお礼を伝えることが、信頼を損なわない大前提です。
たとえばこんな感じで:
- 「お忙しいなか日程調整ありがとうございます」
- 「声をかけてもらえてとても嬉しかったです」
この一言があるかどうかで、その後の空気がまったく違ってきます。
断るときに申し訳なさそうな気持ちを込めすぎると、相手が気を使ってしまうことも。
それよりも、「ありがとう」をしっかり伝えるほうが、前向きな印象につながります。
感謝の気持ちは、断る内容を中和する力を持っています。
参加する意志はある姿勢を見せておく
「今回は行けません」だけで終わってしまうと、「この人、今後も来る気なさそうだな」と思われてしまうかもしれません。
でも、少しだけ先を見据えた言葉を加えるだけで、印象はグッと良くなります。
たとえば:
- 「次回また機会があればぜひ…」
- 「その日は都合が悪いんですが、今度みなさんとランチなどご一緒できたら嬉しいです」
このように、「付き合いそのものを否定しているわけではない」というスタンスを見せるのが大事なんです。
私も何度かこうした表現を使って、「じゃあ次は〇〇で集まろうか」と言ってもらえたことがありました。
人間関係って、“今”より“これから”を見ている人に対しての方が寛容になるものです。
断る場面でも、前向きな姿勢をそっと伝えておきましょう。
言葉にしづらいときは“メッセージカード的メール”も有効
「直接言うのは気まずいな…」
「口頭だとうまく伝えられる自信がない…」
そんなときには、文章で丁寧に気持ちを伝えるのもひとつの手です。
たとえばメールや社内チャットで、少し長めに書いてもOK。
むしろ、きちんと考えた内容が伝わるので、好印象を持たれることもあります。
例文:
件名:【歓迎会のご案内について】
〇〇さん
いつもお世話になっております。△△部の□□です。
このたびは歓迎会にお誘いいただき、ありがとうございます。
とても嬉しいのですが、あいにく当日は家庭の事情で外出が難しく、今回は欠席させていただきたく存じます。
ご準備などお手数をおかけするなか、申し訳ございません。
次の機会にはぜひご一緒できればと思っております。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
こうした“ていねいな断りメール”は、むしろ印象が良くなる場合もあるので、言葉選びに自信がないときはぜひ活用してみてくださいね。
どうしても無理なときは?歓迎会を欠席する“最終判断”
断り方の工夫やタイミングに気を配っても、それでも「どうしても参加できない」と感じる場面がありますよね。
気持ちの余裕がない日もあれば、体調が追いつかない日もある。
そんなとき、「無理してでも行かなきゃ」と自分を追い詰めるのは、むしろ逆効果になってしまいます。
この章では、「最終的に欠席を選ぶときにどうすればいいか?」という視点で、気持ちの整理と行動のヒントをお伝えします。
メンタルが限界なら遠慮せず休んでいい
ときには、頑張りすぎて心のエネルギーが底をついてしまうことがあります。
実際、私も「今日はどうしても人と長く話すのがしんどい…」と感じることが何度かありました。
表面上は元気でも、内心では「行かなきゃ…でも無理かも」と葛藤していたんです。
そんなときは、“今の自分の状態”をちゃんと受け止めてあげてください。
歓迎会は仕事ではありません。
出席が絶対条件ではないイベントです。
その場を無理に乗り越えることで、翌日の仕事や人間関係に悪影響が出てしまっては本末転倒です。
たとえば、「この日は大事なリフレッシュの時間」と割り切って休むことも、ひとつの自己防衛です。
自分のキャパシティを正しく把握して、必要なときにブレーキを踏める人こそ、大人として信頼される存在です。
もしどうしても限界を感じたら、「自分の心を守る」という判断を、堂々と選んでくださいね。
同じ気持ちの人もたくさんいる
歓迎会の断り方で悩んでいると、「こんなことで悩んでるのは自分だけ?」と感じてしまうかもしれません。
でも、SNSや掲示板を見ると、「歓迎会に行きたくない」「断ったけど平気だった」という声が、思っている以上にたくさんあります。
たとえばX(旧Twitter)では、
- 「今日の歓迎会、正直気が重い…」
- 「新人だけど、勇気出して断ったら意外と何も言われなかった」
といったつぶやきが日常的に流れています。
知恵袋や掲示板でも、「参加できないときはどうすれば?」という相談が頻繁に投稿されています。
つまり、歓迎会の参加に迷っているのは、あなただけではありません。
むしろ、「自分の時間やメンタルを大切にしたい」と考える人は、今や多数派になりつつあります。
孤立感を感じる必要はありません。
その選択に共感してくれる人、理解を示してくれる人は、必ず周囲にいるものです。
断ったからといって“すべてが終わる”わけじゃない
歓迎会を断ったことで「職場で浮いてしまうんじゃ…」と不安になる気持ち、よく分かります。
私も、断った次の日にちょっと周囲の目が気になることがありました。
でも、冷静に振り返ってみると、それが「評価に影響した」と感じたことは一度もありませんでした。
むしろ、その後の仕事ぶりや普段のコミュニケーションでちゃんと信頼を得ていれば、誰も気にしなくなります。
大切なのは、一度の選択が自分の価値を決めるわけではないということ。
たとえば、歓迎会に参加したからといって仕事がうまくいくわけではないし、断ったからといって信頼を失うわけでもありません。
職場の人間関係は、日々の行動や言葉の積み重ねで築かれるもの。
飲み会の出欠だけで評価が決まるほど、社会は単純ではありません。
断ったことを気にするよりも、次の日の「おはようございます!」のひと言を、明るく元気に届けてください。
その姿勢こそが、信頼の土台になるんです。
まとめ|歓迎会に行きたくないときの断り方は「配慮×勇気」でOK
ここまで、歓迎会に行きたくないときの気持ちの整理や、実際の断り方について、さまざまな角度からお伝えしてきました。
一番お伝えしたいのは、「行きたくない」と感じること自体、まったくおかしくないということ。
むしろ、自分のコンディションや生活スタイルを大切にしようとする姿勢は、とても自然なことなんです。
たとえ歓迎会を欠席しても、きちんと配慮のある伝え方ができれば、職場での信頼はしっかり保つことができます。
改めて、この記事のポイントを振り返ってみましょう。
・歓迎会を断ってもおかしくない
「参加しない=協調性がない」と決めつける職場ばかりではありません。
むしろ、価値観の多様性を受け入れてくれる職場の方が、これからの時代に合った環境だと言えます。
・断る理由は人それぞれでOK
家庭の事情、体調、予定、気持ちの余裕……どれも立派な理由です。
その中で「相手が納得しやすい表現」を選ぶことが、断るときのコツになります。
・大切なのは“どう伝えるか”
ただ断るのではなく、感謝や気遣いの気持ちをそっと添える。
このひと工夫が、印象を左右する大きな分かれ道になります。
・評価を下げずに断ることはできる
むしろ、誠実で丁寧な断り方をする人ほど「空気が読める人」「信頼できる人」と評価されるケースもあります。
その後のコミュニケーションで誠意を見せれば、関係はきっと良いままで続きます。
・自分の気持ちを尊重していい
職場の空気を気にしすぎて、自分の心を後回しにしなくて大丈夫です。
どうしても参加が難しいなら、その判断に胸を張っていいんです。
私自身も、何度も「今日はちょっと無理かも」と思った日がありました。
でも、断り方を工夫したり、翌日のちょっとした声かけでフォローを入れることで、人間関係がこじれたことは一度もありません。
大切なのは、“行かない”ことではなく、“どう関わるか”という姿勢です。
あなたの時間も、あなたの気持ちも、大事にしていい。
勇気を出して断ったその先に、もっと心地いい職場での関係が築けるはずです。
この記事が、あなたのモヤモヤを少しでも軽くできたならうれしいです。
自分を責めすぎず、丁寧に気持ちを伝えていきましょう。
歓迎会や飲み会の断り方だけでなく、職場の人間関係全般で悩んでいる方も多いはずです。
もっと幅広く、職場の人間関係の悩みや対策を知りたい場合は、こちらの記事もご覧ください。
→ 職場での人間関係の悩みが尽きないあなたへ!心を守るヒントと具体的な対処法を紹介


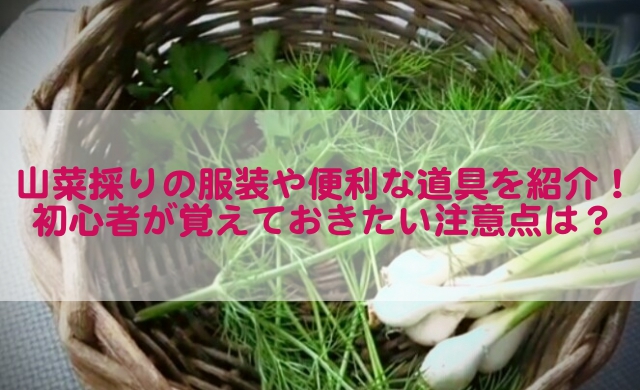
コメント